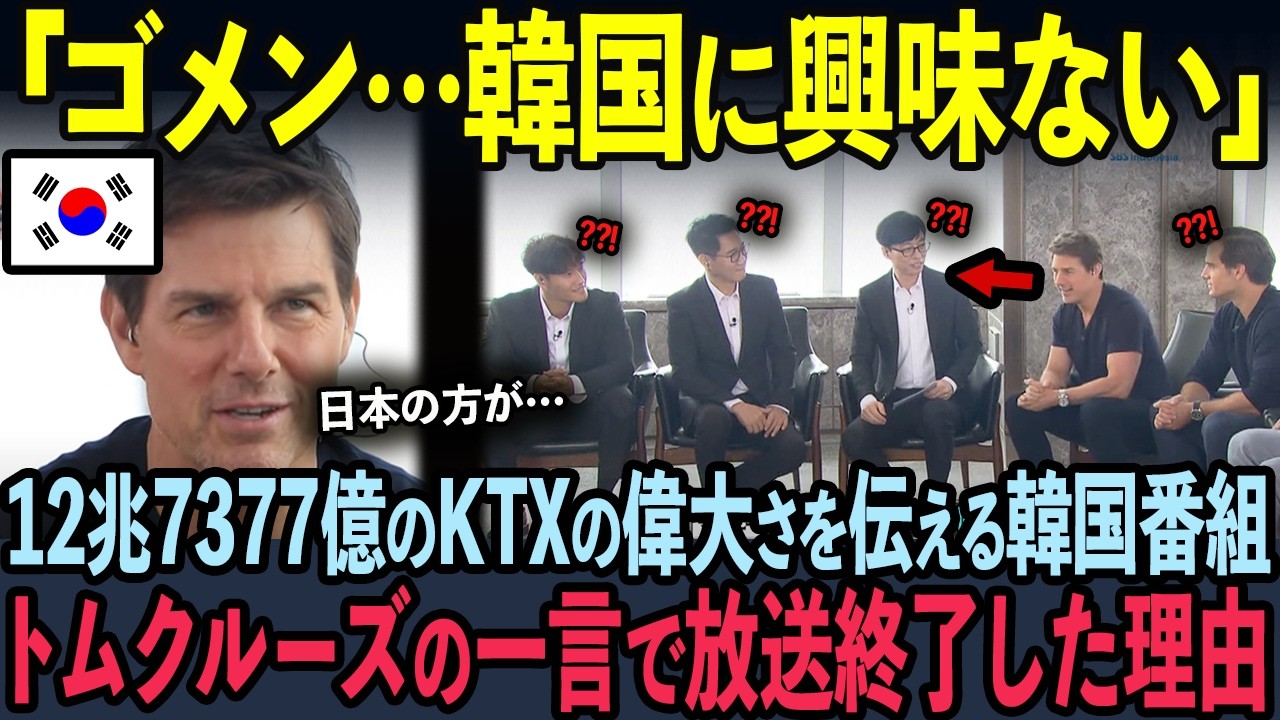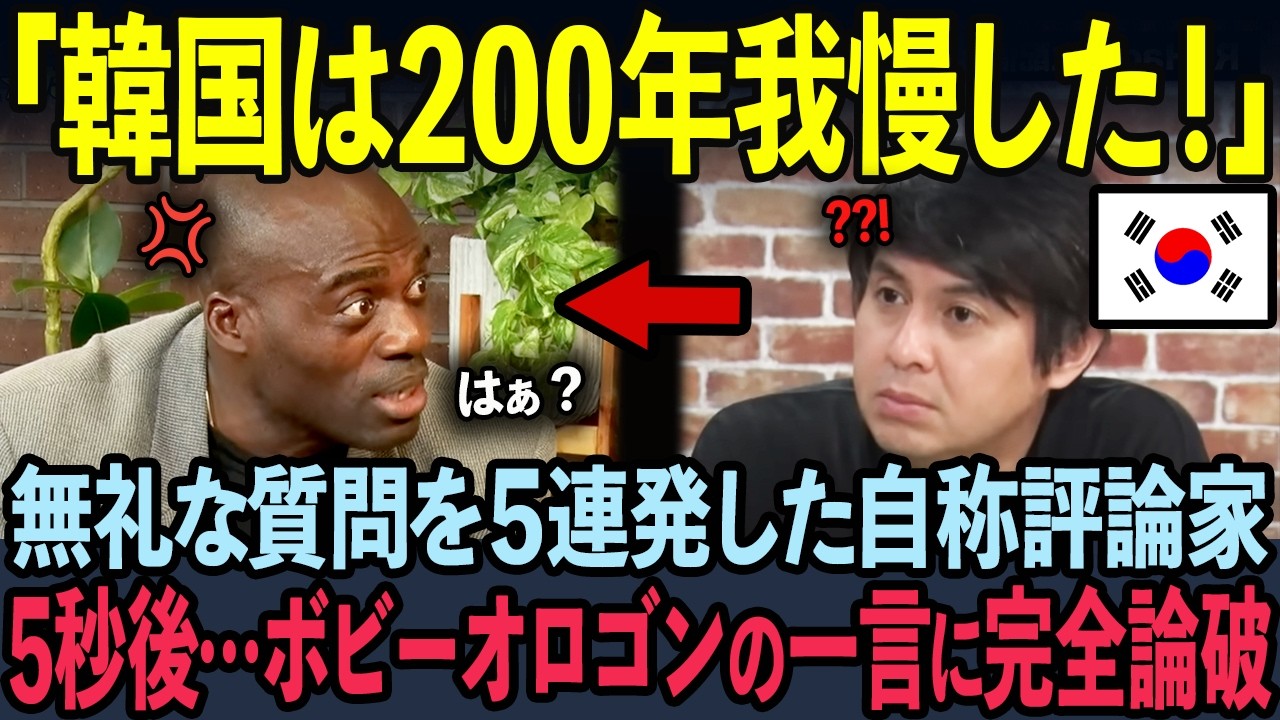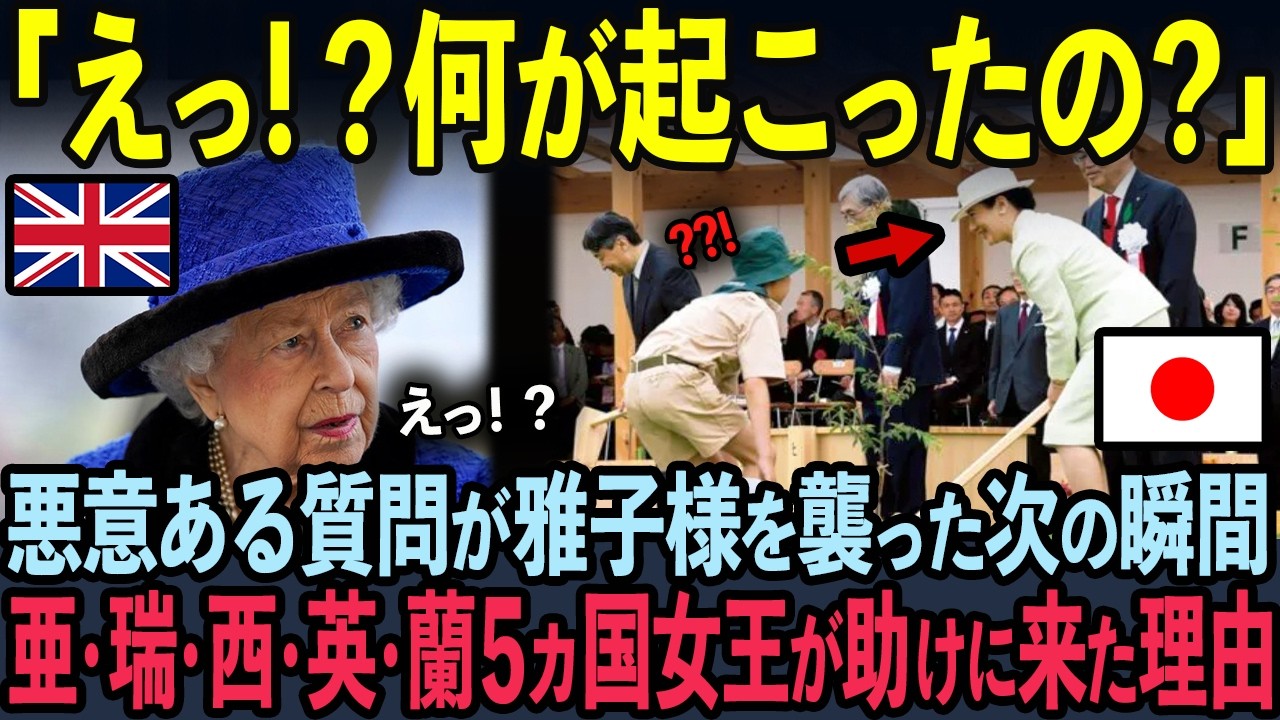中国初のディープシーク(DeepSeek)という生成AIの登場が、AI市場における日本企業の競争力に新たな影響を与えています。ディープシークは、OpenAIの生成AIと同等の性能を持ちながら、開発コストが10分の1以下という驚異的なコストパフォーマンスを実現しています。この技術革新は、日本企業にとって新たな機会を提供する可能性があると考えられます。
 専門家の佐藤氏は、ディープシークの登場が日本企業にとってのチャンスを広げる要因となり得ると指摘しています。特に、AI技術の進化に伴い、学習モデルの構築や文章生成に必要なコストが低下していることが背景にあります。彼は、ディープシークがGPUを駆使して学習モデルを構築している点に注目し、これにより米国企業以外でも高性能なAIを開発できる可能性が示されたと評価しています。
専門家の佐藤氏は、ディープシークの登場が日本企業にとってのチャンスを広げる要因となり得ると指摘しています。特に、AI技術の進化に伴い、学習モデルの構築や文章生成に必要なコストが低下していることが背景にあります。彼は、ディープシークがGPUを駆使して学習モデルを構築している点に注目し、これにより米国企業以外でも高性能なAIを開発できる可能性が示されたと評価しています。
しかし、日本のAI開発においては課題もあります。最新のランキングによると、日本はAI競争力で前年の5位から9位に後退しており、資金調達を受けたAI関連企業数もアメリカには遠く及ばない状況です。このため、日本企業がAI開発でリードするためには、大企業だけでなくスタートアップの育成が重要です。村山氏は、新しい技術やアイデアを生み出すのはスタートアップであり、その成長が日本のAI産業の未来にとって不可欠であると述べています。
さらに、日本のAIスタートアップには言語生成AIを扱う企業が多く存在しますが、開発コストが高いため新規参入が難しい現状もあります。その一方で、自動運転技術に関連する画像生成AIなど、ブルーオーシャンな分野にチャンスが広がっているとの見解が示されています。
一方で、人材不足も深刻な問題です。経済産業省の試算によると、2023年には最大で79万人の人材が不足すると予測されています。村山氏は、AIの進化がこの人材不足を補う可能性があるとしつつも、重要なのは個々のクリエイティビティや挑戦するマインドであると強調しています。また、佐藤氏は、人材育成がブームを先行させるべきであり、逆の順番にならないよう注意が必要だと警鐘を鳴らしています。
総じて、ディープシークの登場は日本企業にとって新たな挑戦と機会をもたらしていますが、競争力を保つためにはスタートアップの支援や人材育成が不可欠です。これからのAI産業の発展に向けて、どのような戦略が取られるのか、今後の動向に注目が集まります。